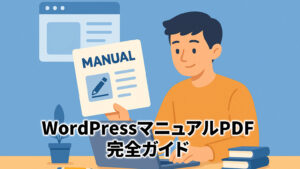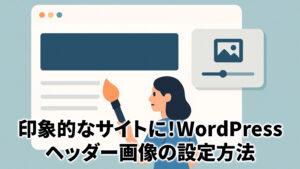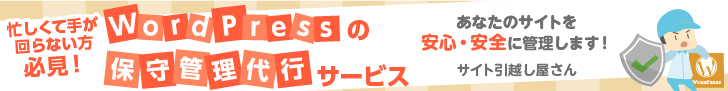WordPressを使っていると「クラシックエディタ」や「ブロックエディタ」という言葉を耳にすることがあります。特に「クラシックエディタはもうすぐ使えなくなる」という話を聞いて不安になる方も多いのではないでしょうか?
この記事では、初心者にもわかりやすく「クラシックエディタはいつまで使えるのか」や「代替手段」について丁寧に解説します。
クラシックエディタとは?初心者でもわかる基本解説
WordPressを初めて使う方の中には、「クラシックエディタ」という言葉を聞いてもピンとこない方が多いかもしれません。これは、かつてWordPressで標準的に使われていた投稿編集画面のことです。
現在は「ブロックエディタ(Gutenberg)」が主流ですが、今でもクラシックエディタを選ぶユーザーは少なくありません。この章では、そのクラシックエディタがどんな特徴を持ち、なぜ今も人気があるのかを丁寧に解説していきます。
クラシックエディタの特徴とは?
クラシックエディタは、WordPressのバージョン5.0以前に使われていた編集画面です。まるでMicrosoft Wordのようなシンプルな見た目と操作性が特徴で、見出し、太字、リンクの挿入などもボタン1つで直感的に操作できます。
たとえば、記事本文を入力して「太字ボタン」を押せばその部分が即座に装飾されるという仕組みで、HTMLやCSSの知識がない初心者にも使いやすい仕様になっています。実際、現在でもこのエディタを好んで使い続けているユーザーは多いです。
反面、最新の機能には対応していないため、レイアウトの自由度や視覚的な表現には限界があります。もし「画像の横にテキストを並べたい」「動画を見やすく埋め込みたい」といった細かいデザインを重視する場合、クラシックエディタだけでは物足りなさを感じることもあります。
Gutenberg(ブロックエディタ)との違い
Gutenberg(グーテンベルク)と呼ばれるブロックエディタは、WordPress5.0から正式に導入された新しい投稿エディタです。文章や画像、見出しなどをそれぞれ「ブロック」として操作するため、視覚的に記事を組み立てることができます。
たとえば、段落、画像、表、ボタンといった要素を1つずつ配置できるので、コードを使わずにデザインの自由度が高まります。特にLP(ランディングページ)や特集記事などをデザイン重視で作りたい場合には、ブロックエディタが向いています。
一方、クラシックエディタに慣れた人にとっては、ブロックエディタの構造が複雑に感じられることも。誤ってブロックを消してしまったり、構成が崩れてしまったりするという声も多く、初心者にとっては最初の慣れが必要です。
なぜ今もクラシックエディタを使う人がいるのか
「なぜ時代遅れのエディタを、今でも使い続ける人がいるの?」と疑問に思うかもしれません。しかし、その理由にはしっかりとした背景があります。
最大の理由は「使い慣れているから」です。特に企業や団体のサイトでは、運用フローが確立されていることが多く、いきなり編集環境を変えることが大きなリスクになります。
また、クラシックエディタを前提に作られたプラグインやテーマがまだ多く存在するため、それらとの互換性を優先してあえて使い続けているケースもあります。さらに、ブログ中心のユーザーにとっては、「書くこと」に集中できるシンプルさが魅力です。
クラシックエディタはいつまで使えるの?最新情報まとめ
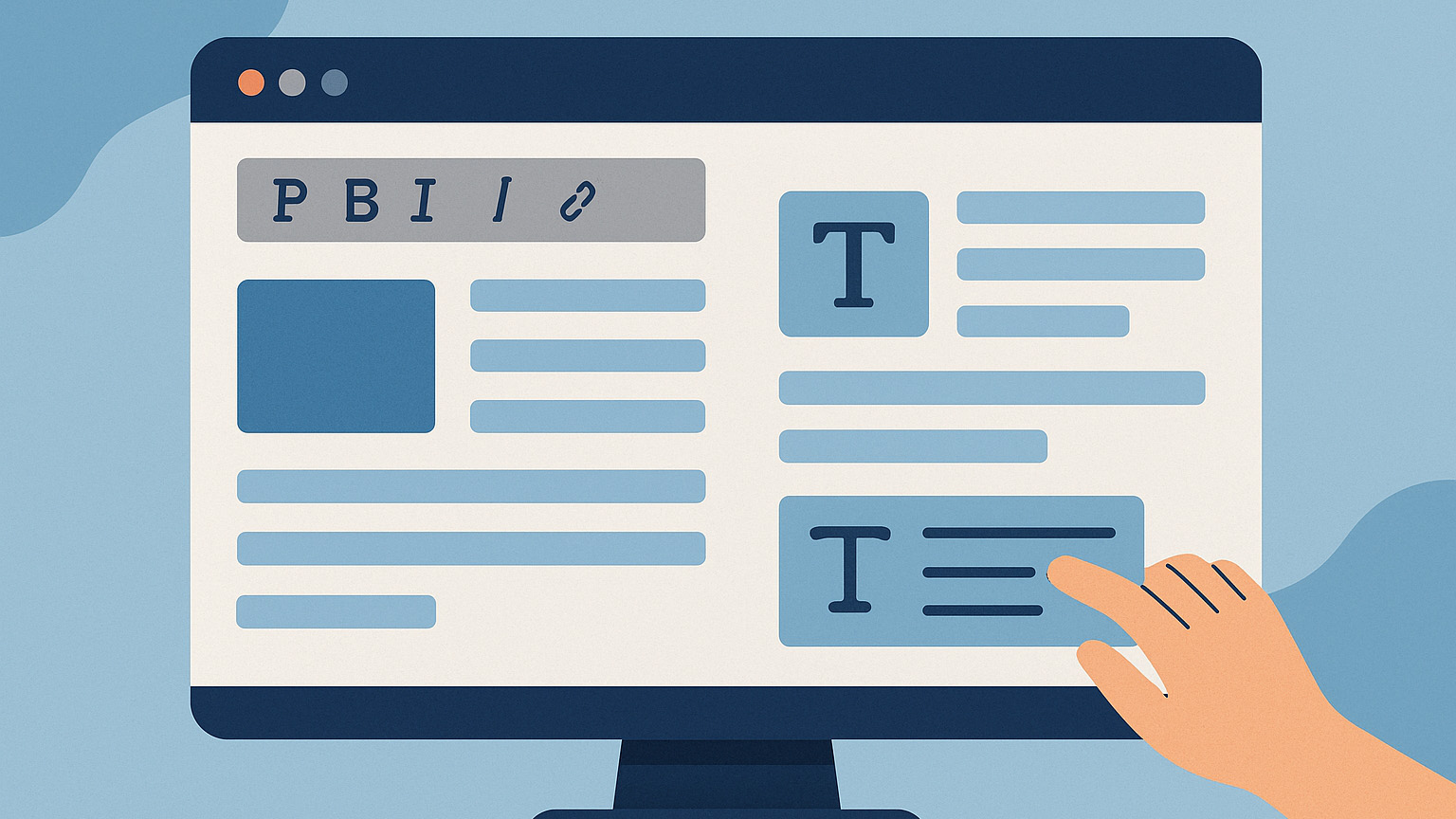
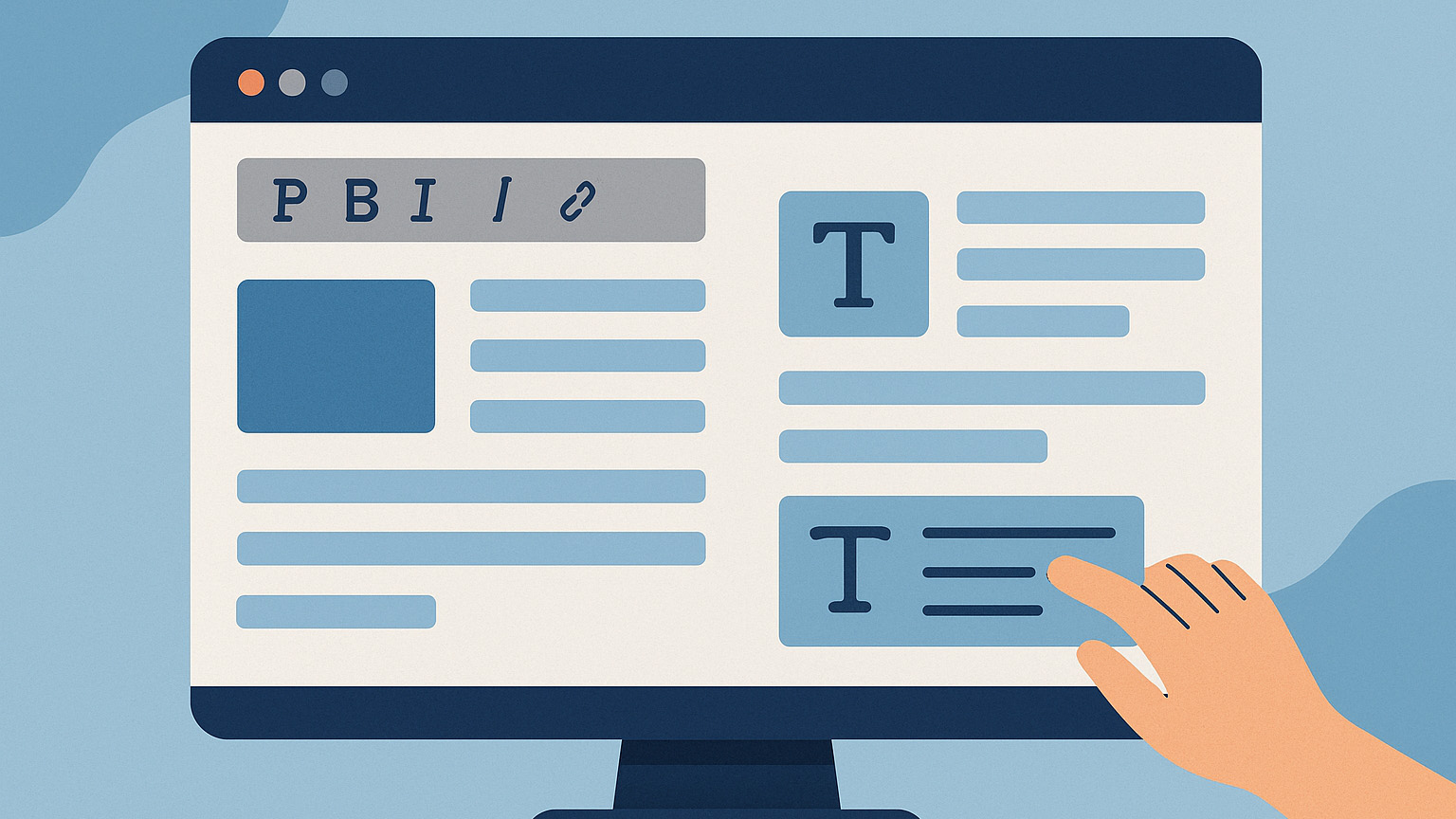
クラシックエディタの今後について「使えなくなるの?」「いつまで使えるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。WordPressの編集環境は進化を続けており、クラシックエディタの扱いにも変化が訪れています。
この章では、WordPress公式の発表や2025年現在のサポート状況、サポート終了後のリスクについてわかりやすくまとめます。
WordPress公式の発表内容
WordPressの公式サイトでは、クラシックエディタのサポートを「少なくとも2024年まで」と明記していました。これは多くのユーザーが急に環境を変えられないという事情を考慮した延長措置です。
そのため、当初の予定よりサポート期間が延び、多くのユーザーがブロックエディタへの移行準備をする時間を得ることができました。とはいえ、これ以降の延長については保証されておらず、公式プラグインの更新頻度も低下しています。
このことからも、クラシックエディタに依存した運用は今後リスクが高まっていくと考えられます。
2025年6月現在のサポート状況
2025年6月現在、クラシックエディタはWordPress.orgのプラグインとして利用可能です。ただし、最終更新日は古く、将来的なバージョン非対応の懸念もあります。
また、WordPress本体のアップデートにより、クラシックエディタとの互換性が少しずつ崩れ始めています。たとえば、ブロックエディタ前提の機能や新しいテーマが増え、旧来のエディタ環境では不具合が出るケースもあります。
このように、表面的には「まだ使える」状態ですが、実際の運用では注意が必要です。特に企業やクライアント向けのサイトでは、将来性を見越した判断が求められます。
サポート終了後も使えるの?そのリスクとは
「サポート終了後も使い続けられるのでは?」と考える方も多いかもしれません。たしかに、すでにインストール済みの環境ではクラシックエディタをそのまま利用することができます。
しかし、次のようなリスクを伴います:
- WordPress本体との互換性が失われる
- セキュリティアップデートが提供されない
- テーマ・プラグインとの動作不良が起こる
とくにセキュリティ面のリスクは重大です。脆弱性が発見された場合でも修正されない可能性が高くなり、サイト改ざんや情報漏えいの原因になります。このような背景から、クラシックエディタを長期間にわたって使用し続けることは、将来的なトラブルの原因になり得ることを理解しておきましょう。
クラシックエディタの代替方法と今後の選択肢
クラシックエディタが使えなくなったらどうすればいいのか、不安に感じている方も多いはずです。この章では、代替手段として使えるエディタや、今後の移行方法について初心者向けにわかりやすく紹介します。
安心してWordPressを使い続けるために、あらかじめ選択肢を知っておくことが大切です。
クラシックエディタのプラグインは今後どうなる?
クラシックエディタは、現在「Classic Editor」という公式プラグインとして提供されています。2025年時点でもインストール可能ですが、更新頻度は減少傾向にあります。
プラグインがWordPressの新バージョンに対応しなくなると、予期せぬエラーや動作不良が起こる可能性が高まります。そのため、長期的に見て依存し続けるのは安全とは言えません。特にビジネスサイトや会員制サイトなど、安定運用が求められる場面では注意が必要です。
ブロックエディタへのスムーズな移行方法
クラシックエディタからブロックエディタへ移行するには、段階的な対応がおすすめです。いきなり切り替えると操作に戸惑うこともあるため、まずは新規投稿だけをブロックエディタで試すと良いでしょう。
既存の記事は「クラシック」ブロックとして読み込まれるため、必要に応じて個別に「ブロックへ変換」を選択し、移行できます。慣れてくれば、柔軟なレイアウトや装飾が可能になるメリットも実感できるはずです。
よくある失敗は、「すべての記事を一括変換してしまい、ブロックの配置が崩れる」ことです。必ずバックアップを取りながら、少しずつ移行しましょう。
他のおすすめエディタやツール紹介
ブロックエディタ以外にも、視覚的に編集できるプラグインが多数存在します。代表的なものとしては以下が挙げられます:
- Elementor(エレメンター):初心者にも人気のドラッグ&ドロップ型ページビルダー
- WPBakery Page Builder:企業サイトやLP制作に適した柔軟性の高いエディタ
- Advanced Editor Tools (旧 TinyMCE Advanced):クラシックエディタに近い操作感を残したまま機能拡張が可能
目的やサイト構成に応じて、最適なエディタを選ぶことが大切です。ただし、ビジュアルビルダー系は一部有料プランもあるため、事前に機能と費用を確認しましょう。
クラシックエディタを使い続けるメリットとデメリット


クラシックエディタは時代遅れと思われがちですが、あえて使い続けるユーザーが今も一定数存在します。この章では、クラシックエディタを選び続ける理由や、その利点とリスクについて客観的に整理して解説します。
導入を迷っている方も、自分に合った運用方法を見極めるヒントになるでしょう。
使い慣れている安心感
多くのユーザーがクラシックエディタを使い続ける最大の理由は「慣れているから」です。とくに長年ブログを運営してきた方や、社内マニュアルでクラシックエディタを使っている企業では、操作感を大きく変えることがストレスになります。
一度慣れてしまえば、投稿の流れが自然と手に馴染み、効率的に作業できるため、新しいツールを覚える必要がないというメリットもあります。業務効率や作業コストを考えると、安心感を優先したい気持ちは理解できます。
テーマやプラグインとの相性
クラシックエディタは、多くの既存テーマやプラグインと高い互換性があります。特に、数年前に開発されたテーマやカスタム投稿タイプは、クラシックエディタ前提で設計されていることが多く、ブロックエディタでは正常に動作しない場合もあります。
このような互換性の問題を回避するために、あえてクラシックエディタを選ぶことで、安定した運用が可能になります。ただし、新しい機能やテーマに乗り換える際には、互換性が問題になるケースもあるため注意が必要です。
将来的なセキュリティリスクとは?
クラシックエディタを長く使い続けることの最大の懸念は「セキュリティ」です。公式のサポートが終了すれば、脆弱性が発見されても修正されなくなる可能性が高まります。
特に、個人情報を扱うフォームや、EC機能を備えたWordPressサイトでは、セキュリティホールが重大なリスクになります。サーバーが攻撃されてデータが流出したり、サイトが乗っ取られたりといった被害は、事業に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
そのため、安全性を第一に考えるなら、サポート終了前に別のエディタへ移行することが推奨されます。
初心者はどうするべき?今から始めるならどっちがいい?
これからWordPressを始めたい初心者にとって、「クラシックエディタとブロックエディタのどちらを使うべきか」は大きな悩みです。この章では、目的や使用環境に応じた選び方をわかりやすく紹介します。
自分のスタイルに合ったエディタを選ぶことで、WordPressをより快適に運用できます。
最初からブロックエディタに慣れるのがベスト?
WordPressの今後を見据えると、最初からブロックエディタに慣れるのが賢明です。なぜなら、公式でもブロックエディタが標準仕様として採用されており、今後の機能追加やテーマ設計もすべてブロック前提で進化しているからです。
初めは少し操作に戸惑うかもしれませんが、慣れると自由度の高さが魅力に変わります。「段落を移動したい」「画像を右寄せにしたい」といった操作がドラッグだけで完了するなど、直感的な編集が可能です。
記事の目的による使い分け方
用途によって適したエディタは異なります。たとえば、日記ブログや簡単な記事更新だけが目的であれば、クラシックエディタでも十分です。一方、デザイン性を求めるLPや企業サイトを構築するなら、ブロックエディタやElementorなどのビルダー系プラグインの方が適しています。
| 用途 | おすすめエディタ |
|---|---|
| 簡単なブログ投稿 | クラシックエディタまたはAdvanced Editor Tools |
| デザイン重視のLP制作 | ブロックエディタ/Elementor |
| コーポレートサイト | ブロックエディタ+テーマ連携 |
個人ブログ・企業サイトそれぞれのおすすめ選択
個人で趣味ブログを運営するなら、操作がシンプルなクラシックエディタから始めて、徐々にブロックエディタに移行するのも一つの手です。初心者向けの無料テーマと併用すれば、最小限の手間でブログを始められます。
一方、企業や店舗の公式サイトを構築する場合は、拡張性や保守性を考慮してブロックエディタやElementorなどを組み合わせた構成が安心です。今後のトラブル対応や機能拡張にも柔軟に対応できるため、プロのWeb制作者もこの方法を推奨しています。
まとめ
クラシックエディタは、初心者にとって扱いやすく、長年愛されてきた投稿編集ツールです。しかし、WordPressの進化とともにその役割は徐々に終わりを迎えつつあります。
2025年時点ではまだ使用可能ではありますが、今後のサポート終了やセキュリティのリスクを踏まえると、移行を視野に入れるべき時期に来ています。この記事では、クラシックエディタの特徴やブロックエディタとの違い、いつまで使えるのか、代替手段、選び方などを詳しく解説しました。
特に初心者の方にとっては「どちらが正解か」ではなく、「どちらが自分の目的に合っているか」を考えることが大切です。これからWordPressを始める方は、最初からブロックエディタに慣れておくことで、将来的にも安心して使い続けることができます。一方、今クラシックエディタを使っている方は、移行のタイミングと方法を見極めながら、自分のサイト運用にとって最適な選択をしましょう。